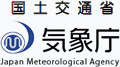極端現象発生頻度マップ
確率降水量の推定方法
1.観測データを使った推定方法
ある極端現象が何年に一回の現象かを推定する際、観測データのように限られた年数のデータしかない場合は、極値統計(ある事象の極値(最大値や最小値等)の統計的な性質を扱う理論)による統計的手法が用いられます。
ある地点Aの日降水量から100年に一回の大雨を推定する例を考えてみます。「XX年に一回の現象」といった極端な現象を調べる場合、毎日の日降水量データは必要なく、年間の最大または最小値といった極値、または一定の値以上のデータを用います。極端現象発生頻度マップの観測データを使った確率降水量の推定では、年間の最大値を用いています。地点Aの日降水量の年最大値(年最大日降水量)データを横軸に、出現頻度を縦軸に整理すると、年最大日降水量の頻度分布が得られます(図1)。分布の右側ほど極端な大雨の事例を示します。地点Aの年最大日降水量データは、極端現象発生頻度マップで用いたデータ(観測結果)と同じく1976年~2023年の48年分しかないとしても、極値統計の理論によれば、このような極値データは、一定の条件を満たしている場合、そのデータ数が多くなれば極値分布と呼ばれる分布に近づくことが知られています。この性質を踏まえ、利用可能な48個のデータに最も合う極値分布を数学的に求めることで、もっともらしい極値分布を推定し、その分布の上位1%の値を計算することにより、地点Aにおいて平均的に1%の確率で発生する、つまり100年に一回の日降水量の値を推定することができます。逆に、ある日降水量が地点Aにおいて何年に一回の現象であるかを推定することが可能です。ただし、あくまで有限の観測データを元にした様々な仮定の下での推定であり、誤差が含まれる点には注意が必要です。
なお、極端現象発生頻度マップの観測データを使った確率降水量の推定では全国一律に、極値分布としてグンベル分布を用いています。平成18年度から令和6年度にかけて提供していた「異常気象リスクマップ」では、極値分布を含む様々な確率分布の中から、観測データに最も適合する確率分布を選択していたため、観測地点によって使用する確率分布が異なっていましたが、全国一律で同じ確率分布を使用することにより、新たな観測データを取り入れる度に選択される確率分布が変わらず、データ更新の影響が小さくなりました。ただし、極値分布を使った極端な降水現象のより良い推定方法については、研究者間でも活発な議論が行われており、その結果も踏まえながら今後も推定方法を見直す可能性があります。

図1 地点Aにおける年最大日降水量の頻度分布
1976年~2023年の年最大日降水量の頻度分布(水色の棒グラフ)と、それに適合させた極値分布(グンベル分布、曲線)。縦軸は出現頻度(%)を、横軸は日降水量(mm)を示します。極値分布のうち赤線部分は、横軸との間の面積(赤色部分の面積)が極値分布全体の面積の1%であることを示します。つまり、黒線と赤線の境目が極値分布の上位1%の場所を示しており、これに対応する日降水量が地点Aにおける100年に一回に大雨(日降水量)と推定できます。
2.予測データを使った推定方法
「用いたデータについて」に記載している通り、予測では1500年分と非常に多数のデータを使用していることから、観測データのように特定の分布系を仮定せず、データそのものの分布から確率降水量の強度や頻度の変化を推定しています。なお、将来の確率降水量の具体的な予測値(日降水量)は、観測データから推定された確率降水量の値に、地域毎の将来変化率(20世紀末(1981年~2010年)を基準とした将来変化率)を掛け合わせることで求めています。ここでの地域は、北海道地方、東北地方、関東甲信地方、北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部・奄美地方、沖縄地方の11地域です。