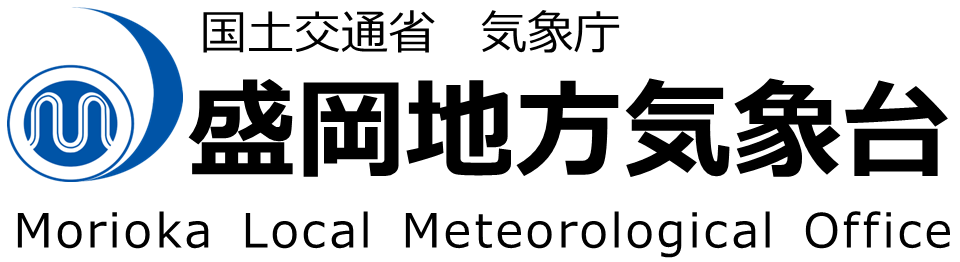盛岡地方気象台長からのメッセージ

盛岡地方気象台のホームページを閲覧いただき、有難うございます。盛岡地方気象台長の蓼沼 信三(たでぬま しんぞう)です。
盛岡地方気象台の所在する岩手県は、東西122km、南北189km、北海道に次ぐ県土面積(15,275km2)を誇り、県としては我が国最大の広さです。気候の特徴は、内陸の西側となる奥羽山脈沿いは、冬季は季節風の影響を強く受け雪が多く、中央部となる北上川沿いは盆地的な気候のため気温の日較差が大きく、特に冬季の厳しい冷え込みが顕著です。北上川の東側となる北上高地の東縁沿岸部は、太平洋側気候で冬季は晴天が多い一方、夏季は冷湿な北東気流、いわゆる「ヤマセ」の影響を受けやすく、現象が強い時には農業をはじめ各方面に大きな影響をもたらしてきました。
このような気候の特徴も、地球温暖化の影響をうけて変化してきており、特に極端な大雨の発生頻度が増えています。岩手県でも、令和5年と6年の8月に線状降水帯が発生して顕著な大雨となる事例がありました。
また、岩手県に大地震をもたらす震源として、三陸沖海底の海溝周辺や、陸地に分布する活断層があり、なかでも規模の大きな地震が海底の比較的浅い深さで発生した場合は津波が発生し襲来することもあります。東日本大震災の記憶は決して忘れることができないものですが、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震を想定した、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」にも注意いただきたいと思います。
さらに、岩手県には4つの活火山があります。特に岩手山は、活動が活発だった平成9~16年頃のあとしばらく沈黙していましたが、山体膨張を示す地殻変動が観測され、令和6年10月には噴火警戒レベルが2(火口周辺規制)に引き上げられました。引き続き警戒が必要です。
このような自然災害から皆さまを守るため、気象庁では観測・予測精度向上にかかる技術開発を推進しています。盛岡地方気象台は、その成果であるさまざまな気象情報を、県民の皆さまへ、適時、的確に届けることを第一の使命としています。しかし、気象台から発表される警報や注意報、市町村から発表される避難指示などに応じて行動するのは皆さまです。気象台では、大雨などの異常時に、皆さまご自身と大切な人の命を守るための行動が的確にとれるよう、防災関係機関や住民の方々に対して、平時から気象情報の利用について解説し、過去の自然災害や防災に関する知識の普及に努めています。
令和7年4月
盛岡地方気象台長 蓼沼 信三