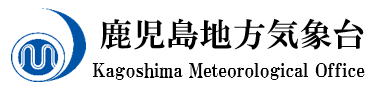この時期の対流圏下層は、北太平洋は高気圧(太平洋高気圧)、アジアは低気圧(モンスーントラフ)となっており、南西から暖かく湿った気流が日本付近に流れ込みやすくなっており、梅雨前線の形成に寄与しています。九州地方は、この南西からの気流が特に流れ込みやすい地域となっており、このことが梅雨期間の降水量が多い一因と考えられます。
九州南部の梅雨の降水量《関連資料》
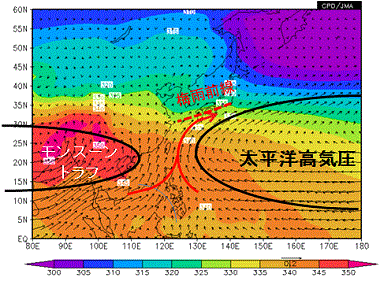
図1 6月の対流圏下層(925hPa)の水蒸気フラックス(黒矢印)と相当温位(℃)(カラー)の平年値。相当温位は暖かく湿った空気の指標。
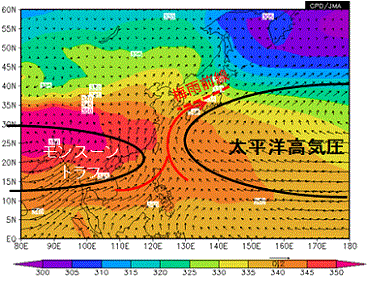
図2 7月の対流圏下層(925hPa)の水蒸気フラックス(黒矢印)と相当温位(℃)(カラー)の平年値。