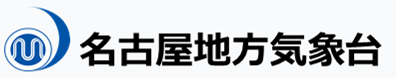みなさま、気象台ホームページをご利用いただきありがとうございます。名古屋地方気象台長の𠮷松和義(よしまつかずよし)です。
名古屋地方気象台は、1890年7月1日に「名古屋一等測候所」として、南武平町(現在の中区栄)で業務を開始し、その後、1923年1月1日に現在地
(名古屋市千種区日和町)に移転して観測・予報のための業務を行っています。現在地で業務を開始してから、2023年1月で100周年を迎えました。
現在も使用している本庁舎は建物の全容だけでなく、塔の形の風速計台、屋根の軒や車寄せの部分、また風速計台の壁面に配された幾何学模様の装飾など、
移転した当時の姿をとどめています。気象台のこの歴史変遷については、「100周年記念特設サイト」として詳細に記載していますので、
こちらのページもご覧いただきたく存じます。
当台の属する愛知県は、比較的温暖な気候で濃尾平野・岡崎平野・豊橋平野といった平地が広いこともあり、農業に適した豊かな土壌に恵まれているだけでなく、
様々な産業活動に適しています。また、北部から北東部は長野県から木曽山脈が南に伸びて三河高原に至り、標高1,000メートルを超える山もあります。
海岸に目を向ければ太平洋、三河湾と接する渥美半島と三河湾、伊勢湾と接する知多半島により長い海岸線を有し、沿岸一体は水産資源に富んでいます。
こうした豊かな自然環境は産業を育む大きな恵みをもたらしてきたと言えるでしょう。一方で、この自然がときに大きな脅威となることも事実であり、
実際、当地も過去には幾多の気象災害や地震、津波による災害に見舞われてきました。
近年でも幾度となく大雨による被害が発生しており、2000年の東海豪雨、2008年の8月末豪雨、そして2020年の7月にも大雨となって、
隣接する岐阜県で大雨特別警報が発表されました。一方、2025年3月に発表された「日本の気候変動2025」において、日本国内の極端な大雨の発生頻度は増加し、
強い雨ほど増加率が高くなっており、1時間降水量80mm以上といった大雨の発生頻度も1980年頃と比較して最近10年では約2倍になっていることが示されています。
地球温暖化の進展により将来にわたって、極端な大雨の発生頻度が増えると予測されており、気象災害に対する備えを一層強化していく必要があります。
また、愛知県では、陸域の浅い地震(内陸地殻内地震)である1891年の濃尾地震や1945年の三河地震、海溝型地震である1944年の東南海地震や1946年の南海地震が発生し、
地震動や津波により甚大な被害が出ています。特に、南海トラフを震源とする海溝型のマグニチュード8~9クラスの巨大地震が30年以内に発生する確率は、
政府の地震調査研究推進本部によれば70~80%と言われています。2024年8月には、日向灘での地震により、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」
が初めて発表され、改めて地震への備えの重要性が認識されたところです。
このような状況のもと、当台では県や市町村等地方公共団体と連携・協力して、平時における防災に関する意識や知識の向上等の取り組みを強化しています。
メディア、国の機関、また研究機関との連携も防災力向上に大切であり、取り組みを続けています。また、顕著な自然災害が発生または発生が懸念されるときには、
地方公共団体等関係機関に職員を派遣して気象情報の提供や解説を行う(JETT:気象庁防災対応支援チームなど)ことにより、関係機関の防災対応を支援しています。
今後とも頼りにされる気象台であるよう、職員一丸となって、関係機関と連携しつつ取り組んでまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
名古屋地方気象台長からのメッセージ
ごあいさつ

令和7年4月 名古屋地方気象台長
吉松 和義