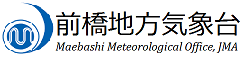前橋地方気象台長からのメッセージ
いつも前橋地方気象台のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
前橋での勤務は2年目に入りました。 大好きな地元群馬県で勤務したいという希望がかない、昨年4月に着任しましたが、今まで勤務してきて思うのは、地元といっても知らないことが多かった、ということです。 県内のそれぞれの地域の特色など、よくわかっているつもりでいましたが、恥ずかしながら着任後に県内をまわって、初めて知ることも多かったです。 気象庁に入庁するまでずっと群馬県で過ごしたので、他県のことは意識しても、群馬県内の地域の特色などは意識することがなかったからかもしれません。
さて、気象庁は、前身である東京気象台が明治8年(1875 年)に観測業務を開始して以来、令和7年(2025年)6月1日に150 年を迎えました。 気象庁の業務は今まで、世の中の技術の発展にあわせて変わってきたところが多いと思います。 観測データの記録については、新しい記録媒体が出現するとそれを採用するようにし、過去のデータも保存のし直しなど行って失われないようにしてきました。 天気の予測にはスーパーコンピューター(スパコン)を使いますが、スパコンもおよそ5年ごとに演算精度の高いものに更新して、より細かい空間スケール、時間スケールの予測ができるようになってきました。 発表する防災情報も現在では多岐にわたっています。気象業務150周年は、このような先人のご努力の積み重ねで迎えることになったと思います。 職員だけでなく、多くの、様々な分野の方々のご尽力により業務が継続されたことに敬意を表します。今後も、時代の変化を取り入れつつも、継続性のある業務を行っていくことがわたしたちの役目と思います。
気象庁では気象業務150周年特設サイトを設け、関連するイベントや情報をまとめて公開しています。 このうち気象業務150周年記念式典上映動画では、各方面からいただいたお祝いのメッセージにあわせ、職員による業務紹介が行われています。 気象庁の幅広い業務を網羅したわかりやすい紹介になっており、わたしのように気象庁に長くいる身でも、新鮮な思いで見ることができる動画です。 みなさまにもご覧いただき、一緒に気象業務150周年をお祝いいただけたら、とてもうれしく思います。
令和7年8月22日
前橋地方気象台長 大和田 浩美(おおわだ ひろみ)

群馬県庁庁舎の入口にある、ツルが舞う群馬県の形をした噴水にて